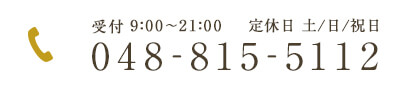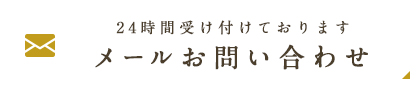- HOME
- 弁護士ブログ
あえてわかりやすく考えてみる検察庁法改正問題
2020.05.13
コロナウイルスの感染拡大防止に自治体が奔走し,国民が苦境に立たされる中,さして緊急性が認められない検察庁法改正案が国会において急ピッチで審議されているようです。
先日のコラムでも言及しましたが,コロナウイルス関係の審議が逼迫する中,桜を見る会問題などについては「今やることではない」と封殺しておきながら,これより重要性も緊急性も認められない検察庁法改正に審議の時間が割かれていることに,与党支持者は疑問を抱かないのでしょうか。
検察庁法改正の問題点は大きく分けて2点,①最近実施された検事長の定年延長の問題と②検察官の定年延長について内閣が介入できるようになるという問題です。
まず①最近実施された検事長の定年延長の根拠規定は国家公務員法であると説明されています。本来国家公務員法の定年延長規定については特別の規定が存在する場合には適用されないと規定されており,その具体例が検察庁法でした。この点は立法時の問答にも記載されていたようです。今回の定年延長はこの点について閣議で解釈変更を行い,国家公務員法を検察官に適用したと政府は説明しています。
しかしこのような適用が可能であるかについては強い疑問が残ります。そもそも国会の立法意思として検察庁法の規定を除外した法律が成立している以上,適用除外の根拠となる検察庁法の規定が改廃されない間は国家公務員法の該当条文を検察官に適用することはできないのではないでしょうか。適用できない場合,本件検事長の定年延長については根拠規定を欠くこととなり,検事総長にも任命できないこととなります。改正後の検察庁法を遡及適用することもないと思われますので,結論は変わりません。
また仮に解釈変更により適用ができるとする場合,解釈変更の理由となる具体的な事実が必要となります。見たところ今回の検事長の件より前に検事長の定年延長が議論されたことはなかったと思いますので,解釈変更を行う理由となる具体的な事実は今回の検事長の件,としか言いようがありません。この点は動かせない事実であるはずであり,内閣もカルロス・ゴーン氏の捜査に関係しているようなことを述べていた記憶があります。しかしそのような事実が解釈変更を必要とする理由に当たるとは考えられません。そもそも検察官は基本的には司法修習の中で選りすぐられた人材が入庁しているはずです。まして検事長になるような方に大きな能力の差があるとは到底思えません。つまり検事長が特定の誰かでなければ勤まらない,というほどに検察庁が人材不足に陥っていることなどあり得ません。同程度の職務を全うする人材は多く存在するはずです。それでも検事長の定年を延長しなければならない具体的な理由を内閣は示せていないと思われます。
この点について例の定年延長と検察庁法改正は関係がないと述べる方も存在しますが,例の定年延長が発端となっていることは明らかであり,そのような意見は,むしろ今回の問題を有耶無耶にしたい無理筋の擁護なのではないかとすら思えてきます。
次の問題は②検察官の定年延長について内閣が介入できるようになるという点です。
この点を理解する前提として,検察官の職務や性質について簡単に説明します。検察官の職務はおおまかにいうと,刑事事件について捜査をすること,裁判所に公訴を提起して公判に立ち会うことです。公訴提起は検察官しかできないこととされています(刑事訴訟法247条)。公訴提起されなければ有罪にもなりませんから,ある意味,検察官は有罪無罪の判断に近い権限を有していると評価できます。この点において検察官の権限は大きく,かつ人権にかかわる重要なものと言えます。別の言い方をすれば,検察官の職務には裁判官のような性質も含まれているということです。
このように検察官は強力な権限を有しているのですが,検察官が訴追する対象にはほぼ制限がなく,現職の国会議員や内閣総理大臣であっても訴追されてしまいます。つまり検察官は時の政権を倒してしまうほどの権力を有しているのです。そのため政権が最も恐れる機関は検察庁といっても過言ではありません。
では政権が最も恐れる検察庁のトップ人事に内閣が口を出せることになったらどうでしょう。まともな思考であれば検察庁の政権に対する追及が鈍ってしまうのではないかと考えるはずです。実際に追及が鈍らないとしても,追及が鈍ってしまうかもしれないという疑いをかけられることが既に大きな問題です。
もちろん検察庁が独善に陥らないための牽制は必要ですが,今回の改正は不当な制度と評価せざるを得ないと思われます。
上記の他にも,今回の解釈変更で検事長の定年にまつわる問題が解決するのであれば国家公務員法が検察官に適用されることになるが,そのことと改正検察庁法との関係はどうなっているのか。今回の改正が必要となるような事実(立法事実)が過去に存在したのであれば,その時に解釈変更や改正の議論がなかった(または不要とされた)のはなぜか。立法事実が過去に存在しなかったのであれば,今回の改正は例の検事総長人事の1点を理由とするものということになり不当ではないか。また問題となっている検事長が検事総長に就任した上で改正検察庁法が適用されるとしたら,いつまで検事総長で居続けることができるのか等,様々な問題が指摘されています。この件は権力の発言を鵜呑みにせず,自分で考えてみる力が試される事案だと思います。
投稿者:
9月入学について考える
2020.05.11
緊急事態宣言により全国の学校が休校となっています。
通常の入学式・始業式は4月上旬ですから,休校期間は1か月以上に及んでいます。そして緊急事態宣言が5月末まで延長される可能性が高いため,既に2か月の休校が見込まれています。
学生にとっての2か月は大変大きいといえます。特に受験を控えた小学6年生,中学3年生,高校3年生にとっては受験までに履修範囲をカバーできない可能性があり,死活問題といえるでしょう。その中でも高校3年生は浪人生との関係では相当のハンディキャップになります。この問題はどうにかしなければなりません。
現在検討されているのは,①緊急事態宣言解除後の残された期間で何とか履修する,②9月入学・始業に制度を変更する,③全員留年する,の3つです。
緊急事態宣言が5月末に解除される可能性が高いことを前提とすると,③については論外だと思います。①については小・中学校のスケジュールがかなり厳しくなると思われますが,その点については特別措置で優先順位の低い履修範囲を削除するなどの手当は可能であると思います。少なくとも夏休みが全くないなどという状況にしてほしくはありません。あれだけ暑い夏の期間に子どもをフルで登校させたら亡くなる子どもが出ると思います。
現在,最も熱い議論が交わされているのは②9月入学・始業への制度変更の可否ではないでしょうか。
この点についての私の意見は,大学だけ9月入学・始業とする制度に変更し,小・中・高校については4月入学・始業のままにするというものです。
小・中・高校を4月入学・始業のままにする理由は,現在の1学期⇒夏休み⇒2学期⇒冬休み⇒3学期という流れに学習ペース上,無理がないと思うからです。学習進度に差が出やすい1学期の早い時期にゴールデンウィークがあり,1学期終了後も長期の夏休みがあることで,遅れを取り戻す機会が充分に確保されています。この流れは学習進度にばらつきが出やすい小・中学校では有効であると思います。
では,なぜ大学だけ9月入学・始業とすべきなのでしょうか。
理由の1つ目は,世界的に9月入学・始業が主流であるということが挙げられます。海外から日本の大学に入学したい方,また日本から海外の大学に入学したい方にとって,日本の大学が4月入学であることは相当な不便になっています。そしてこの不便は日本の大学に海外から優秀な学生を呼び寄せることの障害になっています。世界の大学評価において日本の大学が相対的に低く評価されるファクターのひとつに「国際性」の指標がありますが,入学時期のズレは,この評価を下げる要因のひとつになっている可能性が高いと思います。世界の主流である9月入学とすることで海外の優秀な学生の受け入れが増加し,ひいては日本の大学の評価を高めることができる可能性があります。また日本から海外の大学に進学したい学生の利益にもなります。
2つ目の理由は,大学入試期間の過酷な環境を解消する点にあります。現在の大学入試は1月中旬に1次試験が行われ,2月上旬から下旬にかけて私立大学の入試,2月下旬に国立大学前期試験が行われることになっています。このようなスケジュールの結果,毎年のように雪による開始時間の繰り下げが行われ,受験できない受験生もいます。また体調管理も大変困難な時期です。今年2月には既にコロナウイルスの感染拡大が始まっていたにもかかわらず,入学試験は通常どおり実施されました。何事もなかったかのように扱われていますが,感染した受験生は少なからずいたと思われますし,さらに酷い状況になっていたらどうするつもりだったのか,と思います。
このような過酷な時期に入試を行うのではなく,4月から6月の温暖な時期に実施すれば,これらの不都合は解消されます。
3つ目の理由は,学生に高校時代を充分に楽しんでほしいということがあります。先に述べたように,私は高校については4月入学・始業を維持すべきであると考えています。そうすると高校卒業後,大学に入学する9月まで間が空きますが,この空いた期間に入試を実施するということです。現在の制度では,高校3年の12月までに履修範囲を終えて1月には入試となってしまい,特に中高一貫でない公立高校のカリキュラム上,無理があるだけでなく,高校生活最後の文化祭や部活に集中できないスケジュールになっています。これでは学校の人間関係が最も熟した時期に受験勉強に専念しなければならないこととなり,味気ないと思いませんか?卒業の少し前までは学生生活を満喫できるようにすることは学校行事や部活動を含めた人間教育のためには良いのではないかと思います。
以上の理由から,私は小・中・高校については4月入学とし,大学については9月入学とすることが理想であると考えます。
この制度に対しては,大学卒業後の9月入社には無理がある,という意見があると思います。この点について私は,入社については4月を維持するという意見です。したがって,大学生は7月に大学を卒業した後,8月以降に就職活動を行い,翌年4月に入社することになります。現在の4月入学,4月入社の制度では,事実上,大学3年生の段階で事実上の就職活動を開始し,大学4年生の前期は講義を受講できません。またテレビ局に多いイメージですが,大学3年生の段階で事実上の内定(内々定?)を得ている学生がいるようで,大学3年生と4年生で既に会社の先輩後輩関係になってしまうということがあったようです。大学3年で就職活動を開始するには当然その準備を大学2年の頃から開始しているのであり,これでは大学でほとんど勉強していないに等しいといえます。特に大学4年の1年間はほとんど意味を感じません。このような本末転倒な状況を変えるために,大学4年間は勉学に集中させ,就職活動は卒業後に行うことが望ましいと思われます。このように時間に余裕を持つことで本当に自分の就きたい職業について考えさせ,就職後の短期離職率も下げることができるかもしれません。
このような制度になると高校卒業後の半年間と大学卒業後の半年間の生活費が苦しくなるという指摘もあるとは思います。しかし大学については浪人する方,留年・休学する方も多く,医歯薬系が6年制であることを考えれば,決して非現実的な制度ではないと思います。生活が苦しい学生には給付型の奨学金を充実させることで解決を図るべきです。
いずれにしろ,現在のカリキュラムは教育を受ける権利(憲法26条1項)が予定しているであろう教育効果を上げるためには明らかに無理があります。もう少し余裕を持った制度にできれば,教育を受けた学生の卒業後の人生が,より豊かなものになるのではないかと思います。
「子どもを守れ」のかけ声だけが大きくなる昨今ですが,「子ども」のその後を見据えた制度設計についても議論されるべきではないでしょうか。
投稿者:
「両性」と「夫婦」についてのひとつの考え方
2020.05.09
先日のコラムで憲法24条の改正について書きました。
憲法24条1項は以下のように定めています。
「婚姻は,両性の合意のみに基づいて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」
同条項の「両性」の解釈が問題となっているということはすでに述べました。
では同条項は婚姻における「両性」に「男性と女性」のみを予定しており,「男性と男性」,「女性と女性」を含まない趣旨なのでしょうか。
そもそも24条1項は前段と後段に分けられ,前段で「婚姻の成立に意思表示の合致以外の要件が不要であること」を規定し,後段で「夫婦が本質的に平等であること」を規定しています。このように分解した上で同条項が制定された時代背景を考えれば,同条項が「両性」と表現した理由が多少理解できると思います。
同条項が制定されたのは戦後すぐの昭和21年ですが,同条項が否定しようとしたものはいわゆる家制度と圧倒的な男尊女卑です。そして家制度を否定した先にあるのが「個人主義」であり,圧倒的な男尊女卑を否定した先にあるのが「両性の本質的な平等」です。
家制度の下では婚姻も自由にできず,戸主の同意が必要とされていました。現在も未成年(現在は20歳未満)の子については少なくとも父母の一方の同意が必要とされています(民法737条1項,2項)が,戦前において父母の同意が必要な年齢は女性で25歳,男性は30歳(!)でした。ここまでくると男性差別にも見えますが,婚姻がいかに制限されていたかがわかるかと思います。このような戦前の家制度を否定するために24条1項前段は婚姻の成立要件を当事者の意思表示の合致のみとしました。
さらに戦前においては婚姻後,妻は(民法上の)無能力者とされて,財産は夫に管理されました。また子の親権も夫のみに帰属しました。このような婚姻後の夫婦間における両性の不平等を否定するために夫婦の本質的平等を規定したと考えることができます。
これらの事実を条項の文言との関係で考えると,24条1項が制定された経緯の1つに「両性の本質的平等」があったことから,条文の定め方として男性と女性を対置し明示することが必要であったということがいえます。つまり憲法は両性の本質的平等を規定するため,技術的に「両性」,「夫婦」の文言を使用する必要があったということです。そうだとすれば憲法は婚姻を男女間に限る趣旨までは含んでいなかったと考えることもできるのではないでしょうか。
投稿者:
憲法改正の優先順位
2020.05.05
5月3日は憲法記念日です。
憲法が公布されたのは昭和21年11月3日で,施行されたのが昭和22年5月3日ですので,憲法記念日は憲法「施行」記念日ということになります。憲法が公布された11月3日は文化の日になっています。
現政権は憲法改正を実現するということを言い続けており,令和2年5月3日にも首相が改正の意気込みを述べたと報じられています。その改正内容は9条が念頭にあるようですが,現憲法下における初の改正がいきなり9条というのはハードルが高いように思われます。
まずは現に改正すべき必要性が叫ばれている部分や国民の人権を拡充する方向での改正を行う方が,今後の改正手続も円滑に進むのではないでしょうか。
例えば現在改正する必要があると一部で言われているのは憲法24条1項です。同条項は以下のように規定しています。
「婚姻は,両性の合意のみに基づいて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。」
同条項は婚姻が「両性」の合意のみに基づいて成立すると規定しています。この「両性」の解釈が問題となっているようです。
というのも昨今においては同性の結婚を法的に認める国家も出現しており,日本でも同性パートナーの証明書を発行する自治体があります。こうした流れの中,憲法の同条項に同性婚が含まれるかという議論が起こっています。
ここで1つの考え方として,従来の一般的な語義に基づいて「両性」を解釈するのであれば,男性と女性を示すことにもなろうかと思います。また,その後に「夫婦」とあることからも「両性」とは男性と女性を前提としていると解釈することが素直とも思われます。こうした解釈に基づくならば,憲法は男性と女性の結婚を前提として規定したのであり,同性婚については予定していなかったという結論もおかしくはありません。
しかし憲法が掲げる個人主義(憲法13条)を前提とすると,明文で婚姻を異性間に限定することが整合しているのか,かなり疑問があります。
全ての国民が個人として尊重されるという根源的な理念から出発すれば,個人が望む婚姻形態も尊重されて然るべきであるとの結論に至る方がむしろ素直ではないでしょうか。少なくとも婚姻を異性間に限定した形で規定することで,間接的に同性婚が規定外にあるといった「差」が生じることは憲法が積極的に予定するものではないと思われます。
24条については改めて述べるとして,前述のような意図しない「差」が生まれるおそれを放置するよりも,改正により文言を変更することが望ましいのではないでしょうか。例えば「両性」,「夫婦」を「両当事者」のような文言にするべきなのかもしれません。
このような改正案が国民に提案された場合,果たしてどの程度の投票率となるのか,そして改正案は過半数の賛成を得られるのか,非常に興味があります。
投稿者:
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE